こんにちは、現役文系北大生の各駅停車です。
今回は、恩田陸の小説、『夜のピクニック』を紹介したいと思います。
『夜のピクニック』について
『夜のピクニック』は恩田陸によって2005年に発表された小説です。
学校から100km、ほぼ徹夜で夜通し歩く行事「歩行祭」を舞台に、それぞれ秘密を抱えた高校生3年生たちが、最後の思い出作りにと語り合う内容となっています。
茨城県水戸第一高校の実際にある「歩く会」という行事を元にしていると言われています。
この小説のすごいところは、単調な設定にもかかわらず、面白さが最後まで続くことにあると思います。
「歩行祭」において、何か特徴的なイベントが起きるわけではありません。事件らしい事件は何も起きず、登場する高校生たちは、ただそれぞれの話をしながらひたすら「歩行祭」の行程を歩いていきます。しかし、それでもこの400ページを超える小説は助長性を持たず、最後までその面白さを維持し続けます。
僕は、その理由が、高校生たちの内面が、歩くことで次々に変容していくことを作者の恩田陸が如実に表現したところにあると思います。登場人物たちは、歩くことを通じて、いろいろなことを思い出し、またいろいろなことに気づいていきます。
歩くことを強制され、実際に体を動かしているからこそ見えてくるものを、恩田陸は見事に掬い取っているのです。
「みんなで、夜歩く。たったそれだけのことなのにね。どうして、それだけのことが、こんなに特別なんだろうね。」(p31)
僕の好きな箇所
ここからは、僕が気に入った登場人物の内面描写を数個紹介します。
「当たり前のことなのだが、道はどこまでも続いていて、いつも切れ目なくどこかの場所に出る。
地図には空白も終わりもあるけれど、現実の世界はどれも隙間なく繋がっている。その当たり前のことを、毎年この歩行祭を経験するたびに実感する。」(p24)
「歩行祭」は全行程100kmの長距離をそのコースとしています。それゆえ、日頃生活している場所からははるかに離れた場所へと、生徒たちは足を進めていきます。
実際に現地に行ってみて初めて、地図上にあるものが現実の生活している世界へと地続きでつながっているという実感を得るというのは、現実においてもあるのかもしれません。
「水平線を見ると、いつも大きな誰かが手を広げているところが思い浮かぶ。その人は、手だけがあって、空の上からこちらに手を差し伸べているのだ」(p101)
「歩行祭」の道の中には、海沿いの道も含まれます。
人は、大きく開けた海に向かって開放的な気分を感じることが多いと思いますが、「歩行祭」の中で見る海はそれとはまた違った様相を見せていきます。
広大な開けた海に、大きく包み込むような存在者を登場人物は感じ取っていくのです。そして、その感覚は、次第に恐怖心へと変わっていきます。
「じっと風に吹かれて海沿いの道を歩いていると、自分がこの上なく無防備な存在に思われてくる。何もない空間に向けている身体が、世界に対してむき出しになっているようで、なぜか落ち着かなくなってくるのだ。」
このように、恩田陸は歩くことで変遷していく人間の内面を丁寧に描写していきます。
「日常生活は、意外に細々としたスケジュールに区切られていて、雑念が入らないようになっている。チャイムが鳴り、移動する。バスに乗り、降りる。歯を磨く。食事をする。どれも慣れてしまえば、深く考えることなく反射的にできる。むしろ、長時間連続して思考し続ける機会を、意識的に排除するようになっているのだろう。」(p73)
恩田陸は、小説の中で「歩くこと」と「思考すること」をつなげて考えます。
歩いているうちは、身体は他のことをなかなかすることができません。(「歩きスマホ」も、長時間続けるのは難しいでしょう)
歩くということは、ある意味で身体を考える時間で拘束することなのかもしれません。
そして、恩田陸はこの、長時間歩いて、思考することを貴重なものだと考えていきます。
「長時間連続して思考し続ける機会を、意識的に排除するようになっているのだろう。
そうでないと、己の生活に疑問を感じてしまうし、いったん疑問を感じたら人は前には進めない。
だから、時間を細切れにして、さまざまな儀式を詰め込んでおくのだ。そうすれば、常に意識は小刻みに切り替えられて、無駄な思考の入り込む隙間がなくなる。」(p73)
セネカが『生の短さについて』において、「忙殺されている時間は浪費される時間である」と言っていたのを思い出します。スケジュールを詰めて、やるべきことを増やせば、無駄な思考は生まれません。しかし、無駄な思考と思われていたものが、実は今後生きる上で大切なものだったりする。
『夜のピクニック』においては、歩くこと=体を考える時間で拘束することによって得られた考えが、登場人物を、そして読者に気づきを与えていくのです。
「夜であることに気づくのは、いつも一瞬のことだ。それまではまだ明るい、まだ夕方だと思っていたのに、いつの間にかその比率が逆転していることに驚く。」(p125)
夜になって、「歩行祭」が本格化していく中で差し込まれるこの文章。
身体を動かすことに集中して、意識が外界から切れていく。と思ったら今度は外界の景色が見えなくなって、自分の内面に帰っていく。こういった意識の往還関係が、登場人物に「夜」を気づかせるのを遅らせます。
「歩行祭」において重要な要素の一つとなるのが、自身の身体のメンテナンスです。
およそ100kmの道を歩き切るには、自身の足裏や、ふくらはぎの状態に定期的に意識を向けていかなければなりません。そういった生身の身体に対する意識があるからこそ、外界と内面の意識の往還も「歩行祭」ではいっそう起こりやすくなっていくのです。
以上、『夜のピクニック』の書評をしていきました。「歩行祭」のように、歩いて遠くに行くということは、生身の身体で時間の流れを感じる事であり、それはただ机にすわって過ごした時間とは別の質感を持って、人間の内面に現れていくのだと、僕は通読して感じました。


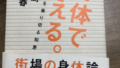

コメント